ジャワ(インドネシア🇮🇩)
8-9C シャイレンドラ朝
928-1223 クディリ朝
1222-1292 シンガサリ朝
1293-1520 マジャパヒト王国
【東】
16C末-1755 マタラム王国
【西】
1527-1813 バンテン王国
歴史、学びメモ
ジャワ(インドネシア🇮🇩)
8-9C シャイレンドラ朝
928-1223 クディリ朝
1222-1292 シンガサリ朝
1293-1520 マジャパヒト王国
【東】
16C末-1755 マタラム王国
【西】
1527-1813 バンテン王国
『創世のタイガ』
言葉の想像。(こうかな?)
アサンテ ありがとう
カリブ どういたしまして
ウタム おいしい
トゥリア 大丈夫
ンジェ なぜ
フィカ 煙
ンゴジャ やめろ?
ケレレ 待て?
アドゥイ 敵
エンダ 行く
アケメネス朝ペルシア(BC550-BC330)
・建国者 初代国王 キュロス2世
前550 メディアから独立し、メディア、リディア、新バビロニアを征服。
都:スサ
・2代目 カンビュセス2世
前525 エジプト征服 オリエント統一
・3代目 全盛期 ダレイオス1世
王都 ペルセポリス(儀礼用)
・サトラップ(知事)制
20州に派遣。さらに王の目、王の耳(監察官)がサトラップを監視。
・王の道(スサ〜サルデス(トルコ))
アラム人やフェニキア人の貿易奨励。
・ペルシア戦争
前490 マラトンの戦いで敗れる
・ダレイオス3世
前330 アレクサンドロス大王により滅亡
ペルシア文字
ゾロアスター教
アッシリア帝国(前663-前612)
都:ニネヴェ
前663 オリエント初統一
サルゴン2世
アッシュル=バニパル
ニネヴェ図書館 楔形文字
世界初の図書館
(中島敦『文字禍』)
駅伝制
前612 新バビロニアとメディアの連合軍により滅亡。
世界史漫画の年号
前16C頃 エジプト『王家の紋章』
前1466 エジプト『海のオーロラ』
前7C-前1C 中国『史記』
前343- ギリシア『ヒストリエ』
前216 ローマ『ヘウレーカ』
1002 北欧『ヴァンランド・サガ』
1213 モンゴル『天幕のジャードゥガル』
14C イスラム、アラビア『バットゥータ先生のグルメアンナイト』
1491 イタリア『チェーザレ』
1553 イギリス『セシルの女王』
1618 ドイツ『三十年戦争』
1741-1796 ロシア『女帝エカテリーナ』
1755-1793 フランス『ベルサイユのバラ』
漫画『女帝エカテリーナ』3巻 メモ
アゾフ、オデッサ、セヴェストーポリ、コンスタンチノープル
アレクサンドル・ランスコーイ
プラトン・ズーボフ
ロシアがポーランドへ侵攻。
→オスマン帝国とロシアの数十年の戦いへ発展。
仏はトルコにロシアを攻めさせた。
1768-1774
第一次ロシア=トルコ戦争
エルミタージュ美術館
隠れ家の意味。仏ルソーにならって。
1772 第一回ポーランド分割
ロシア、オーストリア、プロシアで分ける。
1773-75 プガチョフの乱
(百年前のステンカ・ラージンの乱さながら)
ロシア南部から北上。
1978(49才)孫誕生。後のアレクサンドル1世。
1783年(54才)アレクサンドル・ランスコーイ亡くなる。
その後、アレクサンドル・マモーノフとクリミア旅行へ。トルコの怒りを買う。
1788-93 第二次ロシア=トルコ戦争
1789 フランス革命には反対の姿勢
コシューシコ
ポーランドの対ロシア反乱。鎮圧される。
1795年
第三次ポーランド分割
共和主義の取り締まり。
1796年(67才)逝去。
漫画『神聖ローマ帝国三十年戦争』1巻メモ
1618年
ドイツ、ライン地方
神聖ローマ帝国の領邦の一つファルツ領。
ファルツ選帝侯領。ハイデルベルク。
君主フリードリヒ5世
妻エリザベート(エリザベス・ステュアート)
(ジェームズ1世の娘)
選帝侯
神聖ローマ皇帝を選ぶ選挙権を持つ諸侯。マインツ、ケルン、トリーアの三大司教とファルツ伯、ボヘミア王、ザクセン公、ブランデンブルク辺境伯の七諸侯。
国務相ゾルムス伯
官房長アンハルト公
神聖ローマ皇帝マティアス
ボヘミア王フェルディナント
1618年 ボヘミア・プラハ城
プロテスタントのクーデター
三十年戦争開始
コミック文庫・漫画『女帝エカテリーナ』2巻
著者:池田理代子 原作:アンリ・トロワイヤ
(メモ)
エカテリーナ2世 18C啓蒙専制君主
1729-1796(67才没)
在位1762-1796(33才-67才)
副宰相ミハイール・ヴォロンツォーフ伯
姪
姉:エリザヴェータ・ヴォロンツォーヴァ
妹:エカテリーナ・ヴォロンツォーヴァ
VS
宰相ベストゥージェフ伯
スタニスワフ・ポニャトフスキ
英・プロシア
VS
仏・オーストリア
ロシアは仏と条約を結んだので、敵はプロシア・フリードリヒ2世。
権謀術数(けんぼうじゅっすう):はかりごと
北アメリカでの英仏の植民地争い
↓
1756-1763 七年戦争へ
(墺が普からシュレージエンを取り返そうとした。)
オルローフ家
長男:イヴァン
次男:グリゴーリー
三男:アレクセイ
四男:フョードル
五男:ウラジーミル
1762年 エリザヴェータ女帝崩御
ピョートル3世即位
↓
七年戦争で敵として戦っていたプロシアと停戦。
プロシア側に付く。
・キケロ・・古代ローマの政治家・哲学者。哲学を学び、理性的に生きれば、一生のいかなる時期も憂いなく生きることができると説いた。
・プルタルコス・・古代ギリシアの哲学者・著述家。プラトン哲学の流れ。
・マルクス・アウレリウス・・五賢帝最後のローマ皇帝。ストア派の哲学者。自らを律し、他人や環境に左右されずに、常に自己を成長させようと努力した。
・セヴィニエ夫人・・仏貴族。書簡作家
唯々諾々(いいだくだく):人の言うことを何でも承諾し、逆らわないさま
侍女のエカテリーナはダーシュコヴァ夫人となっている。
アレクセイを出産。
オラニエンバウム。
グリゴーリー・ポチョムキン
1762年
クーデター
エカテリーナ2世即位(33才)
国境隣接ポーランド アウグスト3世
トルコ(ギリシア正教会発祥の地コンスタンティノープル)
ムスターファ3世
イヴァン・アントノーヴィチ
(イヴァン6世)
■ ロシアの皇帝(ツァーリ)
| 在位期間 | 君主名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1547–1584 | イヴァン4世(雷帝) | 初代「ツァーリ」。専制君主制を確立。 |
| 1584–1598 | フョードル1世 | イヴァン4世の息子。子がなく断絶。 |
| 1598–1613 (動乱時代) |
多数の僭称者と短命政権 | ボリス・ゴドゥノフ、偽ドミトリー1世・2世など。 |
| 1613–1645 | ミハイル・ロマノフ | ロマノフ朝創始者。貴族の支持で即位。 |
| 1645–1676 | アレクセイ・ミハイロヴィチ | ミハイルの息子。「ロシア法典」を整備。 |
| 1676–1682 | フョードル3世 | アレクセイの息子。短命。 |
| 1682–1696 | イヴァン5世 & ピョートル1世(共同統治) | イヴァンは名目上の君主。実権は後にピョートルへ。 |
| 1696–1725 | ピョートル1世(大帝) | 単独統治に移行、西欧化を推進。ロシア帝国を創設、西欧化を推進。1721年に正式に「皇帝(インペラートル)」の称号を使用。 |
|
1725–1727 |
エカチェリーナ1世 |
ピョートル1世の妻。 |
|
1727–1730 |
ピョートル2世 |
ピョートル1世の孫。若くして死去。 |
|
1730–1740 |
アンナ |
ピョートル1世の兄イワン5世の娘。 |
|
1740–1741 |
イヴァン6世 |
幼児皇帝。廃位されて幽閉。 |
|
1741–1762 |
エリザヴェータ |
ピョートル1世の娘。 |
|
1762 |
ピョートル3世 |
エリザヴェータの甥。即位後半年で |
|
1762–1796 |
エカチェリーナ2世(大帝) |
啓蒙専制君主、ロシアの黄金時代を築く。 |
|
1796–1801 |
パーヴェル1世 |
エカチェリーナ2世の息子。暗殺される。 |
|
1801–1825 |
アレクサンドル1世 |
ナポレオン戦争で勝利、神聖同盟結成。 |
|
1825 |
コンスタンチン |
正式には皇帝ではないが、継承問題の |
|
1825–1855 |
ニコライ1世 |
保守的な統治。クリミア戦争勃発。 |
|
1855–1881 |
アレクサンドル2世 |
農奴解放令を発布。暗殺される。 |
|
1881–1894 |
アレクサンドル3世 |
反動的政策を実施。 |
|
1894–1917 |
ニコライ2世 |
最後の皇帝。ロシア革命で退位し |
ロマノフ朝 系図
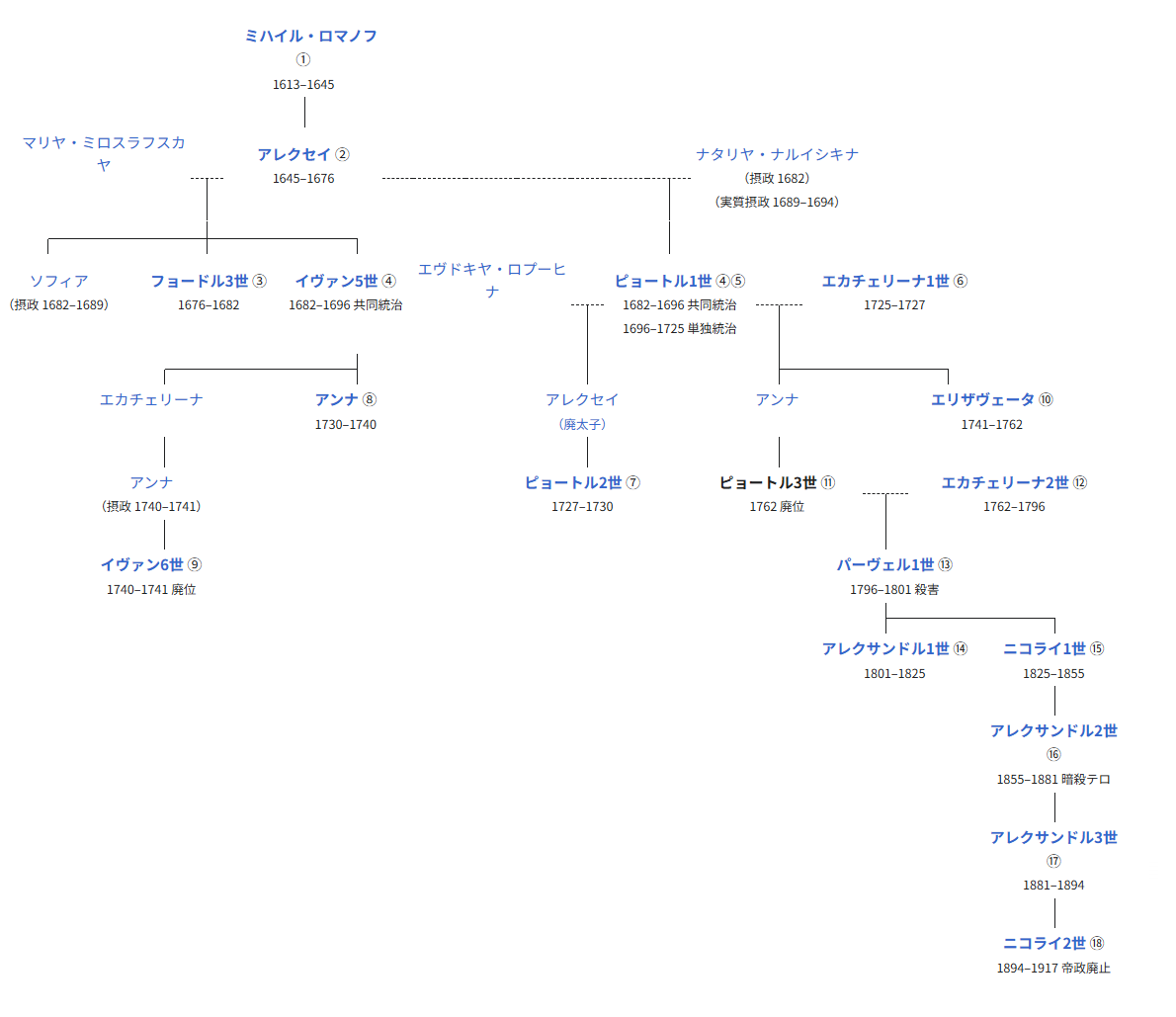
(Wikipedia)
コミック文庫・漫画『女帝エカテリーナ』1巻
著者:池田理代子 原作:アンリ・トロワイヤ
(メモ)
エカテリーナ2世 18C啓蒙専制君主
1729-1796(67才没)
在位1762-1796(33才-67才)
ゾフィー・フォン・アンハルト=ツェルプスト
シュテッティン(神聖ローマ帝国)の貴族の娘。
現・ポーランド
(シュテッティンからトリエステまで。(鉄のカーテン))
クリスチアン=アウグスト公の第一皇女。
アンハルト=ツェルプスト家。
母の実家、ホルシュタイン=ゴットルプ家。
ロシア皇帝と縁深い。
母ヨハンナの兄はエリザベータの婚約者だった。
コルネイユ(悲劇)、ラシーヌ(悲劇)、モリエール(喜劇)
フランス古典文学(17C)
ピョートル3世は、ピョートル大帝の孫。ホルシュタイン家。
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
ピョートル1世=エカチェリーナ1世
| |
アンナ(姉) エリザヴェータ(妹)
|
ピョートル3世=エカチェリーナ2世
(Wikipedia)
18C当時ヨーロッパは絶対主義国家の完成期。
中央集権的な国家統一と植民地活動により、国家間の対立が色濃くなっていた。
・イギリス ハノーヴァー朝 ジョージ2世
・フランス ブルボン朝 ルイ15世
・プロシア※ ホーエンツォレルン家 フリードリヒ2世
(※プロイセンの英語名)
・オーストリア ハプスブルク家 マリア・テレジア
・ロシア ロマノフ朝 エリザヴェータ女帝
1743年頃?ゾフィーが14才でロシアに来たころ、
ヨーロッパではオーストリア継承戦争(1740-1748)の最中。
オーストリア VS プロイセン
(→アーヘンの和約で墺はシュレジェン地方をプロイセンに割譲)
ロシア二大勢力
・反プロシア
副宰相ベストゥージェフ
VS
・親プロシア・仏
ラ・シェタルディー候
ゾフィー(エカテリーナ2世)は、プロシア大王、フリードリヒ2世の推薦で(=大王のロシアへの思惑を背負って)ロシアへ嫁いだ。
都:ペテルブルグ
ピョートル3世はプロイセン・フリードリヒ大王に傾倒。
エカテリーナはルター派からロシア正教に改宗。ロシア語も学ぶ。
エカテリーナ=アレクセーエヴナと改名。
ラズモフスキー伯
エリザヴェータの側近
1745年 婚礼(エカテリーナ16才)
シベリア
シュリュッセルブルグの牢獄
チョグローコヴァ夫人
ヴォルテール(仏)
啓蒙主義
偉大で先進的で合理的な思想。
セルゲイ・サルトゥイコフ
レオン・ナルィシキン
1754年 25才
パーヴェル1世誕生
1688 名誉革命
英ジョン・ロック『政治論二編』『統治論』
立憲君主制を理想とする→憲法に従って行われる君主制。君主の権力が議会の制限を受ける。
仏・モンテスキュー『法の精神』三権分立『ペルシア人への手紙』
仏・ヴォルテール『哲学書簡』
英国大使・ウィリアムズ
スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキ伯爵(ポーランド)
英は仏と不和。ロシアに近づきたい。
また英はプロシア陣営でもある。
英・プロシア VS 仏
↓
ロシアを引き入れたい