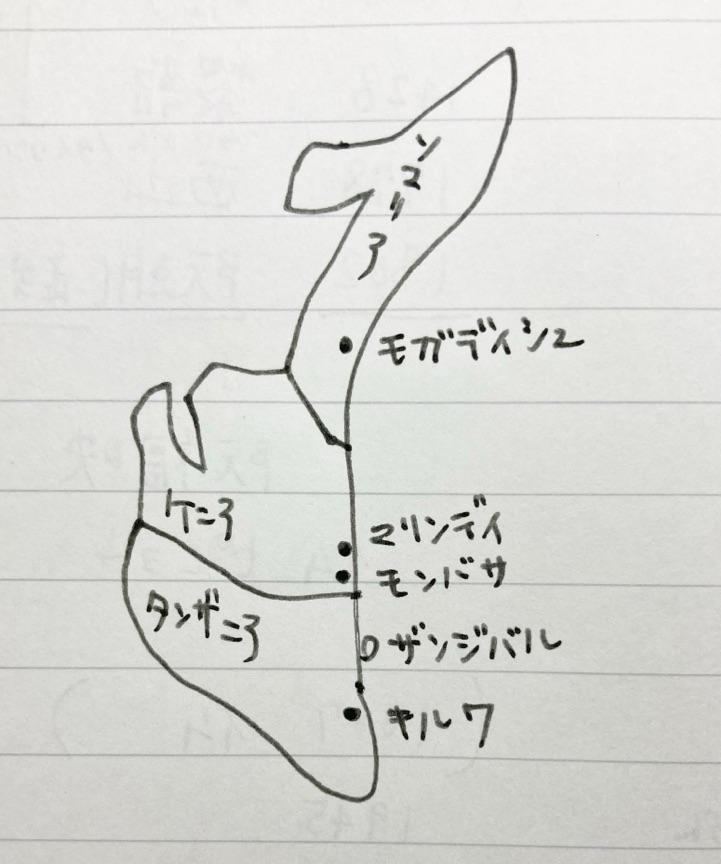【47】現代文明と各地の紛争
(1)アフリカの紛争
(2)パレスチナ問題の行方
(3)イラク・アフガニスタン情勢
(4)現代の文化と人類の課題
(1)アフリカの紛争
ポイント①アパルトヘイトに苦しむ南アフリカ!
人種差別に立ち向かったマンデラとその苦悩
<ジンバブエ>
・ローデシアの独立
白人政府によるアパルトヘイト政策の実施
→黒人が解放戦線を結成
↓↓
・ジンバブエ独立・・黒人政権
(ローデシア(白人)→ジンバブエ(黒人)に改名)
<南アフリカ共和国独立>
・イギリス連邦より離脱
国連総会が対南ア経済制裁を決議
・アフリカ民族会議(ANC)の抗議活動
・アパルトヘイト諸法撤廃(1991)
↓↓
・全人種による大統領選挙の実施(1994)
マンデラ大統領(任1994~1999)
元ANCの指導者
南アフリカ初の黒人大統領
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ポイント②紛争が続くアフリカ諸国
民族、宗教、地下資源・・絶えることのない紛争
<旧ポルトガル領からの独立>
1970年代、ポルトガル国内で民主化。それに連動してアフリカの国が3つ独立。
[1]ギニアビサウ独立
[2]アンゴラ独立
[3]モザンビーク独立
→いずれの国も、政府派 VS 反政府派の内戦へ・・
<アフリカ諸地域の紛争>
・ナイジェリア内戦(ビアフラ戦争)
東部に住むイボ族がビアフラ共和国を建国
(石油が取れる地域)
・ソマリア内戦(1980年代~)
多数のグループによる武装闘争が激化
→武力行使を認められた国連PKOの派遣→失敗
無政府状態に・・(1991~2012)21年間
海賊行為で公海を荒らす
・ルワンダ内戦(1990~1994)
フツ族によるツチ族の大量虐殺
(2)パレスチナ問題の行方
ポイント①第4次中東戦争後の和平への動き
エジプトの下した決断とアラブ諸国の反応
<エジプトとイスラエルの歩み寄り>
・中東和平合意
カーター大統領(米)の仲介
イスラエル首相:ベギン
エジプト大統領:サダト
(第4次中東戦争。現実主義者。エジプトを守るため動いたが・・)
・エジプト=イスラエル平和条約の締結
エジプトがアラブ諸国の中で初めてイスラエルを公式に承認
↓↓
アラブ諸国からは猛反発。断交など。
↓↓
・サダト大統領暗殺(1981)
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ポイント②ついに解決!?パレスチナ暫定自治協定!
20世紀末に調印された協定の「理想」と「現実」
<1980年代のパレスチナ>
・シナイ半島返還(1982)
イスラエルから→エジプトへ返還
関係が良くなると思いきや・・
↓↓
・イスラエルのレバノン侵攻
パレスチナ解放機構(PLO)の本部を攻撃
↓↓
・インティファーダの開始
パレスチナ人の大衆的抵抗運動。メディアで国際世論に訴える。
<イスラエルとパレスチナの歩み寄り>
・パレスチナ暫定自治協定の締結(オスロ合意)(1993)
イスラエル首相:ラビン
PLO議長:アラファト
(クリントン(米)/ 引き合わせたのはノルウェー、米)
↓↓
・パレスチナ暫定自治政府の樹立
ガザ地区などで自治が始まる
↓↓ しかし・・
・ラビン首相暗殺(1995)
この後イスラエルは和平へ消極的になっていく・・
(アラブ人に強気な方が支持率が上がる)
・アラファト議長の死去(2004)
・ガザ地区はイスラエルのシャロン首相により壁が作られ、隔離された・・。(2023年10月~ガザとイスラエルは再び戦闘に・・)
(3)イラク・アフガニスタン情勢
ポイント①アメリカに踊らされた!?イラクの動向
サダム・フセインの暴走とアメリカの思惑
<サダム・フセイン大統領(任1979~2003)>スンナ派
イラン革命。ホメイニ。第2次オイルショック。(1979)
↓↓
・イラン・イラク戦争(1980~1988)
米がイラクを支援。(米はイランが嫌いなので)
↓↓
・クェート侵攻
→湾岸戦争(1991)
ブッシュ(父)大統領。多国籍軍の派遣。
・米軍、イラク攻撃(イラク戦争)(2003)
ブッシュ(子)大統領。
大量破壊兵器の保持を口実にイラクへ侵攻。
→フセイン政権の崩壊
→米軍がイラクにとどまる。米軍駐留。
民主政治を導入するも・・スンナ派、シーア派、クルド人が混在しているため、民主政治ではまとまらない。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ポイント②国際テロ組織をかくまっていた!?アフガニスタンの行方
闇が深いアフガニスタン情勢
<アフガニスタン(社会主義政権)>
・ソ連軍、アフガニスタンへ侵攻(1979)
→社会主義政権を擁立
→アメリカの反発
→内戦状態へ・・(ソ連の財政圧迫)
<アフガニスタン(ターリバーン政権)>
・ソ連軍、アフガニスタン撤退(1988~1989)
ゴルバチョフ書記長
↓↓
ソ連がいなくなったあと、アフガニスタンでは・・
→イスラーム武装勢力:ターリバーンが首都を制圧
・同時多発テロ事件(2001.9.11)
アメリカはアル・カーイダ(国際テロ組織)の犯行と断定。
→アフガニスタンのターリバーン政権が、アル・カーイダをかくまっていると断定。
→米軍、アフガニスタン攻撃。
→ターリバーン政権の崩壊
→米軍、撤退。
→再度、ターリバーン政権が復活
※イラクもアフガニスタンも、米の軍事介入で政権が崩れた。現在も情勢は混乱、不安定。
(4)現代の文化と人類の課題
ポイント①20世紀の文化
激動の世紀を反映した文学・芸術・哲学とは
<哲学・精神分析>
・フロイト(墺)・・精神分析学
「夢はあなたの精神状態を表しているんです」
・デューイ(米)・・プラグマティズム(実用主義)
「哲学は実生活で使えないと意味がないんだ」
→教育学
<経済学>
・マックス・ヴェーバー(独)
「カルヴァニストあるところに資本主義あり」
カルバンを賞賛
<文学>
・シュペングラー『西洋の没落』
・トーマス・マン『魔の山』ファシズムを批判
<芸術>
・ピカソ『ゲルニカ』
・ジャズ・・米で生まれた黒人音楽
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ポイント②科学の進歩と人類にとっての大きな「課題」
発達する科学の裏側で悲鳴を上げ続ける「宇宙船」
<20世紀を代表する技術・発明>
・自動車(発明は19C末)一般への浸透
ラジオ、映画
・飛行機、人工衛星、クローン技術、生命工学(バイオテクノロジー)
<科学の躍進>
・アインシュタイン
相対性理論を提唱
第二次世界大戦後、核兵器の廃絶を訴える
<環境問題(環境破壊)>
・人口爆発と飢餓
・オゾン層の破壊、地球温暖化、砂漠化
・環境と開発に関する国連会議(地球サミット)
開催地:リオデジャネイロ(ブラジル)
「持続可能な開発」にむけての国際会議
・京都会議(地球温暖化防止会議)の開催(1997)
温暖化の原因の、温室効果ガス(二酸化炭素)の排出量を減らそう
→日本やEU諸国は議定書に批准
→米(ブッシュ(子))・中国は批准を拒否
(先進国だけ厳しい!と不満)
→ロシアの批准(2005)
「京都議定書」の発効