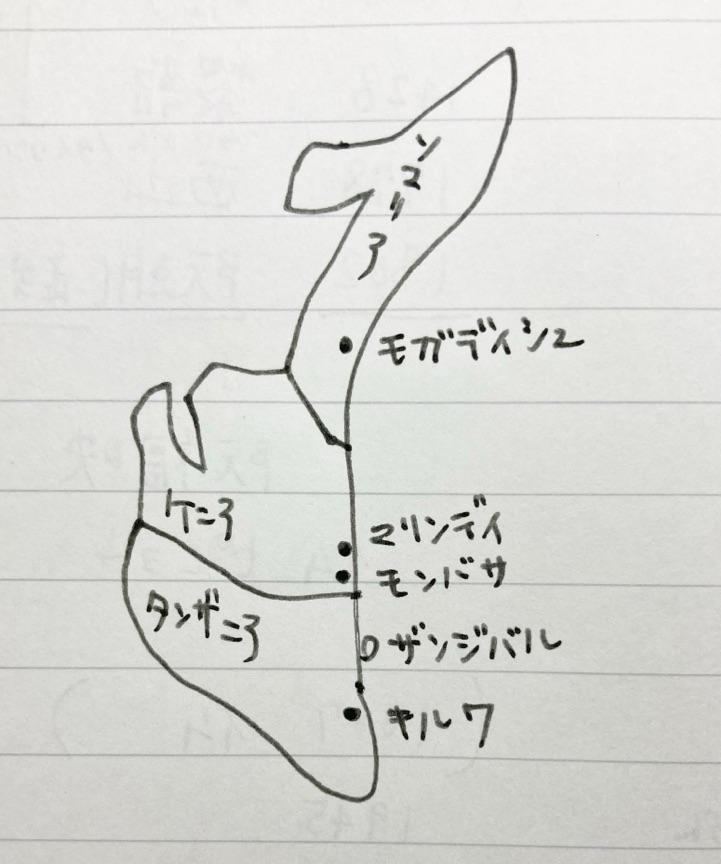【11】中世ヨーロッパ世界の成立
成立期の中世ヨーロッパ世界をみる視点
(1)ゲルマン人の大移動
(2)フランク王国の発展
(3)第2次民族移動の時代
(4)封建社会の成立
(1)ゲルマン人の大移動
■ ゲルマン人の生活
古ゲルマン社会
ライン川、ドナウ川の北
先住のケルト人を圧迫しながら居住地域を拡大。
・民会(最高議決機関)
・従士制(有力者に忠誠を誓う)
・キリスト教が広まる(異端:アリウス派)
■ 西ローマ帝国の命運
ゲルマン人の大移動(4~6C)
フン人の侵入。(匈奴の一派?)
ゲルマン人を圧迫。
・西ゴート人が南下開始(375)
ゲルマン人の大移動スタート。
西ローマ帝国に保護を求めて入ってくる。
・カタラウヌムの戦い(451)
西ローマ・ゲルマン〇 VS ✕フン人(アッティラ大王)
フン人の侵入を止めた。
・西ローマ帝国滅亡(476)
✕←ゲルマン人傭兵隊長オドアケル
■ ゲルマン人国家の乱立
なぜ短命なのか。
・西ゴート王国
イベリア半島
→ウマイヤ朝が滅ぼす(711)
・東ゴート王国
イタリア半島。テオドリック大王。
→ビザンツ帝国・ユスティニアヌス大帝が滅ぼす
・ヴァンダル王国
北アフリカ
→ビザンツ帝国・ユスティニアヌス大帝が滅ぼす
・ブルグンド王国
ガリア(仏)東南
・フランク王国
ガリア(仏)北
・ランゴバルド王国(ロンバルディア王国)
北イタリア
・アングロ=サクソン七王国(ヘプターキー)
大ブリテン島に建国
七つの国
エグバートの統一(829)
=イングランド
(2)フランク王国の発展
■ なぜフランク王国は長生きしたのか?
⇒改宗、防衛、ローマ教皇へ接近の3つ。
ローマ系住民や教会との関係。
〇フランク王国(481~843)約360年
(前半)
メロヴィング朝(481~751)
・クローヴィス(481~511)(建国)
異端アリウス派から、正統アタナシウス派に改宗
・トゥール・ポワティエ間の戦い(732)
ウマイヤ朝(イスラーム)✕ VS 〇フランク王国
宮宰(王のサポート)カール・マルテル
(後半)
カロリング朝(751~843~987)
・ピピン
ピピンの寄進(756)
ランゴバルド王国を攻撃し、ラヴェンナ地方を教皇へ献上
⇒ローマ教皇領の起源
■ 西ローマ帝国の復活?
・カール1世(カール大帝)シャルルマーニュ(位768~814)
(アッバース朝・ハールーン・アッラシードと使節を交換)
領土的にも文化的にもローマを復活させようとした
旧西ローマ帝国領土の回復
・ランゴバルド王国征服(北イタリア)
・ザクセン人(北ドイツのゲルマン人)の平定
・アヴァール人(アジア系遊牧民)を撃退
・カロリング=ルネサンス
古典文化(ローマ)の復興にも力を尽くした。アルクイン(英・神学者)を招く。キリスト教の発展、ローマ文化。
(都:アーヘン)
・伯(地方行政を担当)
巡察使を派遣して監察。
「伯爵」の語源。
・カールの戴冠(800.12.25)
ローマ教皇レオ3世がカール大帝に「ローマ皇帝」の帝冠を授ける。
⇒名目上「西ローマ帝国」の復活。
「ゲルマン」・「ローマ」・「キリスト教」の3要素の結合した世界を
「中世・西ヨーロッパ世界」と言う。
・ヴェルダン条約(843)
東フランク・西フランク・中部フランク
・メルセン条約(870)
東フランク・西フランク・中部フランク
ドイツ・フランス・イタリアの原型に
・東フランク(843~911)
カロリング朝の断絶→ザクセン家から王を選出。ザクセン朝。
↓↓
・神聖ローマ帝国(962)
オットー1世
マジャール人(アジア系遊牧民)を撃退。
ローマ教皇からローマ皇帝位を授与。(カール大帝がもらった冠と同じ状況)
・西フランク(843~987)
カロリング朝の断絶→パリ伯ユーグ=カペーが国王に。カペー朝。
・中部フランク
早くにカロリング朝の断絶→近代まで分裂状態
ほぼ同じ頃に・・↓↓
■ また民族の侵入?
第2次民族移動の時代。
・ノルマン人(北のゲルマン人)(ヴァイキング:入り江の民)
8Cから気温が下がってノルマン人が南下。
現住地:スカンディナヴィア半島、ユトランド半島。
デンマーク王国、ノルウェー王国、スウェーデン王国を建国。
海上ルートで移動。
〇ロシア
・ノブゴロド国(862)
リューリク(建国)。
ルーシ族(ノルマン人の一派・ロシアの語源に)を率いて建国。
↓↓
ノブゴロド国の将軍が南下。
・キエフ公国(862)
ドニエプル川流域。
〇北フランス
・ノルマンディー公国(911~1066)(現在・仏ノルマンディー地方)
ロロ(建国)
〇イギリス
アングロ・サクソン七王国が統一(イングランド王国)
アルフレッド大王がデーン人を撃退。
↓↓
・クヌート(1016~1035)(デーン人王子)再度、英を攻める。
(『ヴィンランド・サガ』)
イングランドを征服。イギリス、デンマーク、ノルウェーを支配。北海帝国。
↓↓
クヌートの死後、再びアングロ・サクソン系が支配
〇南イタリア
両シチリア王国(1130~1860)
古代ローマ以来の商業ルートが復活していく。
(4)封建社会の成立
■ 自らを守るための工夫
国王・諸侯・騎士の契約関係。
フランク王国の分裂、ノルマン人の侵入など、不安定な時代。
・封建制度
恩貸地制度(ローマ末期)+従士制(古ゲルマン)
(自分の土地を寄進して、そこから借りる。)
主君は家臣に封土(領地)を与える
↓↑ 双務的契約
家臣は主君に軍役の義務を負う
階層制(ヒエラルヒー)
・国王・・形式上のリーダー
・諸侯・・広大な支配領域と家臣を持つ有力者
(諸侯から選ばれた代表者が国王。学級委員長みたいな。国王の力はそんなに強くはない。)
・騎士・・騎乗して戦
※「封建時代」は自分の土地、財産を守るための工夫。みんなで守っていこうという制度。その守りたい「土地の話」がこちら↓↓
■ 西ヨーロッパは閉ざされた世界
荘園における農民の生活とは
・荘園(領主の所有地)
一つの村のようなもの。
〇2種類の土地
・領主直営地・・領主が直接経営した土地。
・農民保有地・・領主が農民に保有させた(=貸す)土地。
・不輸不入権(インムニテート)
国王の課税権や裁判権などの行使を、領主が拒否する権利。荘園内は閉ざされている。
・領主裁判権
領主が農民に対して行使した裁判権。理不尽でも絶対的。
・農奴(領主に隷属する農民・小作人)
賦役・・領主の土地を無償で耕作
貢納・・収穫物の一部を領主に収める(家賃)
十分の一税・・教会への税
結婚税・・結婚で領外に出る場合納入
死亡税・・相続税
閉鎖的な村で唯一の情報発信者が教会。
ローマ教会の発言を妄信的に信じていく。